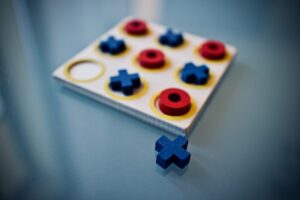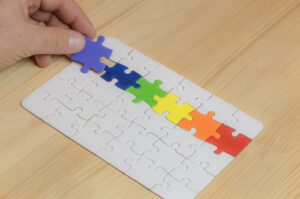なぜ「満足していたはずの顧客」が、静かに離れていくのか?
顧客満足度調査の結果を見ると、決して悪い数字ではない。
大きな不満も見当たらない。
それでも、利用が減り、更新されず、いつの間にか関係が途切れている。
こうしたケースは、BtoCでもBtoBでも珍しくありません。
このときよくある解釈は、「特に不満はなかったが、なんとなく離れた」というものです。
しかし、その“なんとなく”の裏には必ず理由があります。
ただし、その理由は通常の顧客満足度調査ではほとんど見えてきません。
顧客満足度調査がとらえているのは「今、残っている顧客の声」
顧客満足度調査(CS調査)は、現在も商品・サービスを利用している顧客を対象に実施されます。
そのため、把握できるのは、「今、何に満足しているのか」「どこに不満を感じているのか」「今後も使い続けたいと思っているか」といった、「現在進行形の評価」です。
「すでに利用をやめた人」「気づかないうちに離れていった人」の声は、CS調査では把握しにくい領域にあります。
過去ユーザーが語るのは、「不満」ではなく「ズレ」
離脱した顧客に話を聞くと、必ずしも強い不満が語られるわけではありません。
よく聞かれるのは次のような声です。
- 思っていたほど、自分には合わなかった
- 期待していた使い方とは少し違っていた
- 他社の方が、今の状況には合っていると感じた
ここで重要なのは、評価の基準が「満足か、不満か」ではないという点です。
判断の軸になっているのは、「最初に何を期待していたか」とのズレです。
「離脱理由」は、関係が終わった後にしか言語化されない
利用中の顧客は、多少の違和感があってもそれを明確に言葉にしないことがあります。
「まだ様子を見よう」「そのうち慣れるかもしれない」――こうして違和感は、判断されないまま蓄積されていきます。
そして、「利用をやめる」「契約を更新しない」といった行動としての決断が下された後に、「なぜ離れたのか」「どこが合わなかったのか」が、初めて整理され言語化されます。
つまり、離脱理由は「過去ユーザー」になって初めて語られるものです。
なぜ“過去ユーザー調査”が必要なのか
この「関係が終わった後の声」を拾うために有効なのが、過去ユーザーを対象としたアンケート調査です。
この調査の目的は不満点を洗い出すことではありません。
本質的な役割は次の3点にあります。
① 判断に至ったプロセスの整理
→ なぜ使い続けなかったのかを時系列でとらえる
② 初期期待とのズレの把握
→ 何が合わなかったのかを明確にする
③ 再接続の可能性の見極め
→ どんな条件が整えば再び選ばれる余地があるのか
これは、「満足度調査の代替」ではなく、顧客理解を補完するための調査と位置付けることができます。
BtoC/BtoBで異なる実施方法、共通する視点
過去ユーザー調査の進め方は、BtoCとBtoBで異なります。
| BtoC | 無記名で心理傾向を把握、セグメント別に再アプローチの示唆を得る |
| BtoB | 記名式で取引履歴と紐づけ、個別対応・営業改善につなげる |
ただし、ここでも聞くべき視点は共通です。
- 当初、何を期待していたのか
- どこでズレを感じはじめたのか
- 他社を選んだ理由は何だったのか
- どんな改善があれば、再検討の余地があるのか
これらを整理することで、離脱は「失敗」ではなく、次の改善につながる情報に変わります。
初回の期待を知らなければ、離脱の意味は解釈できない
過去ユーザーの声は、とても重要です。
しかし、それだけを切り取っても、十分ではありません。
「何を期待してはじまり」「どこでズレが生じ」「最終的に、どんな判断に至ったのか」――この流れは、新規顧客対象アンケートで扱った「初回の気持ち」とセットで見ると、より理解しやすくなります。
次回は、新規・既存・過去ユーザーという複数の声を、どう“つなげて”理解するか――顧客理解を「地図」として描く方法をご紹介します。
🔷 無料相談のご案内
もし、「離脱理由を、感覚ではなく構造としてとらえたい」「過去ユーザーの声を、改善や再接続につなげたい」
と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
初回の期待から離脱に至るまでの流れを整理し、自社に合った調査設計と活用の方向性を、一緒に考えます。
【こちらの情報もおすすめ】
顧客満足度調査(CS調査)とは?|基礎から活用まで解説
新規購入者/離脱顧客対象アンケート
顧客満足度調査を設計するときに迷いやすい「2つの調査タイプ」の考え方
お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]
ご相談・お問い合わせ